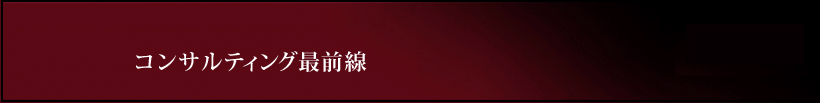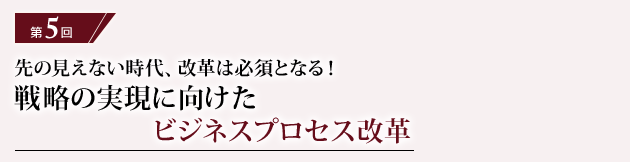人材という資産を残す! JMACのアプローチ

基本構想の共有化、実践段階での具体的なフォローというJMACならではのBPR手法をすでに紹介した。飯田は、さらにJMACの特徴として人材育成をあげる。「BPRは、以後も継続的に行われるべきものです。いつ、状況が変わり、ビジネスプロセスを見直すことになるかもしれません。経営体質を変えるには、社内にBPRを実行できる人材が、どうしても必要なのです」JMACではクライアント側の人材と、ともにプロジェクトを進める形式を取る。クライアントは自然とJMACのノウハウを学びつつ、自社の課題を解決することになる。「人材という資産を残していく方針は、意識して行っていることです。副次的なものですが、これもBPR実施成果のひとつといえるでしょう」
このほかにも、初期段階で、業務レベルに落とし込める事業戦略であるかどうか、再確認をしておくなど、現実的な展開を踏まえたアプローチがJMACには多い。また業務の見直しというと、現状分析のために長い時間を割き、最初に膨大な資料を用意するケースがある。だが、JMACではそうした手法は採用していない。プロジェクトの進行に合わせて必要な現状分析を行っているという。「進行具合を意識し、段階に応じて必要な調査をしています。いきなり、多すぎる情報を渡されても、クライアントは混乱するばかりです。すすめ方も、現実的で効果の高い方法を選ぶのがJMAC流です」
それぞれの現場から見えてきた改革の必要性
BPRと事業戦略、業務の再構築は強い関係があり、切り離せないものだ。飯田が手がけた事例には、それを痛感させたものがいくつもあるという。「ひとつは業務の効率化を依頼された案件でした。しかし、現状分析をしてみると、その背景には顧客層の変化があったのです。これまで小規模の発注が多かったところへ、大型店舗をもつ企業が進出したため、発注の規模も求められる最優先事項も変わってしまいました。古い業務システムでは対応しきれなったことが、根本原因だったのです。これまでの顧客をターゲットとするのか、それとも新しい大口の顧客をターゲットとするのか、事業戦略の確認をしました」そのクライアントは、最終的に洗い出されたビジネスチャンスを活かし、事業戦略に反映したという。
「もうひとつは、ある全国展開している企業で各支店の業務効率化を行う案件です。効率20%向上という数値を課せられていましたが、支店で起きている業務の不具合をどれだけ改善しても、この数字を達成するのは不可能でした。そこで、必要なのは個々の業務の改善ではなく、その前提となっている構造そのものの改革ではないかと考えました」その企業では、どこの支社でも同一の業務システムとサービスを行っていた。しかし、地域差もあって各支店で最適化されているとはいい難い事実を、飯田は現地の視察から知っていた。「顧客から見て、必要なサービスを支店ごとに見直し、20%の人員削減を前提に人員配置を行いました。すべての支店で、同一の機能をもつ必要はありません。顧客の利用モデルを洗い出して、重点化と簡略化を行いました」業務システムの見直しは、本社の役割だ。このリデザインの結果、飯田は20%の数字を実現することができた。顧客視点は現場から生まれてくるが、それを実行に移せるのは本社であることを飯田は学んだという。
優秀な人材を発掘し活かす BPRによって競争力はまだまだ伸びる

BPRの効果としてもっとも大きいもの―― それは競争力の向上だ。経営的視点をもって部門間の調整を行える、BPRを推進できる人材がどれだけ社内にいるのか? それによって競争力に違いが出る。日本企業は、これまでそうした人材を得る機会が少なかった。人材不足という問題は、根本的に解決できるのだろうか?「多くのクライアントと接した実感では、BPR改革の才能と意欲をもった若い人材は意外と多いと思います。従来は、彼らはその能力を伸ばす場所がありませんでした。若いときからやっていれば、将来的に自社のBPRを担うことは充分可能だと思いますね」
また、経営トップの間でも、BPRの必要性を感じ始めている人は多いのではないか、と飯田は指摘する。「特に業績悪化などが問題のない企業でも、このままではいけないのでは、と漠然とした危機感を持っているように見受けられることがあります」隠れた人材が活躍できる場を用意し、継続的なBPRのスキルを手に入れる。その実現を含めて、JMACがサポートできることは多いと飯田は考えている。「BPRが可能なら、競争力はまだまだ伸ばすことができるでしょう。そのポテンシャルを現場から感じますね」正解をつきつけるだけのコンサルティングは、真に問題を解決することはできない。本質的な解決を目指そうという信念が、JMACの“BPR”にはこめられているのだ。
![]()
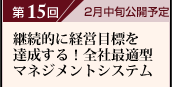
文化と気質の違いを超え、新たなる形に進化した日本の技術と、イタリアのコンサルティング事情もご紹介いたします。