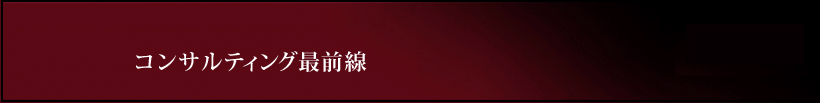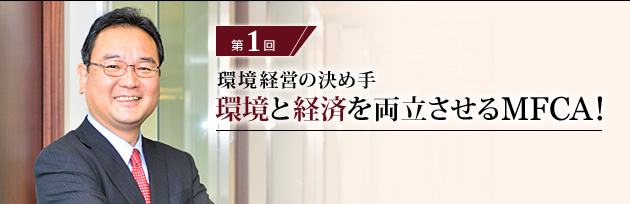- 下垣 彰 (しもがき あきら) チーフ・コンサルタント
- 研究、開発、技術革新を主な領域としてきたが、2004年度より経済産業省から委託を受けた、環境管理会計手法のMFCAの研究と普及事業を行っており、MFCAの適用ノウハウが非常に豊富である。またその経験により、経済産業省よりMFCAの国際標準化作業委員会委員の委嘱を受け、MFCAの国際標準化にも貢献している。
- MFCAとは
- マテリアルフローコスト会計(Material Flow Cost Accounting、略してMFCA)は、製造プロセスにおける原材料のロスに着目して、そのロスに投入した原材料費、加工費、設備償却費、エネルギー費などを“負の製品のコスト”として、総合的にコスト評価を行う原価計算、分析の手法。MFCAを使って分析、検討されるコストダウン課題は、省資源や省エネにもつながる。
環境保全と同時に企業利益も追求する『Eco-Ecoマネジメント』

真の“環境経営”は、環境負荷の軽減と企業利益が両立していなければならない。JMACでは、京都議定書が話題になった10年ほど前から、環境経営をテーマに研究会をもっているが、そのなかで、環境への貢献によって企業経営への負荷が高くなるといった問題が指摘された。経営に負担をかける取組みは短期間で終わりやすいので、結果、環境への効果はあまり期待できない。そこで、企業が環境対応を持続することで、利益を生み出せる構造が必要だと考えた。『Eco-Ecoマネジメント』は環境(Ecology)にプラスなことが、経済(Economy)にもプラスになるというJMACが提案する環境経営の概念だ。モノづくりの分野での実現手段として、環境管理会計のMFCAがある。
MFCAは難しい手法ではない どう活用するかが命題
MFCAを用いることでコストダウンができるのは、これまで“無駄”になっていたマテリアルを“見える化”するからだ。環境にとって負担となる廃棄物を低減させ、生産コストを下げることができる。環境管理会計という枠組みと、製造工程におけるコスト評価という特徴から難解なものと思われるかもしれないが、MFCAの計算自体はさほど難しいものではない。JMACでは、経済産業省の委託事業のなかでエクセルを使ったMFCAの簡易計算ツールを開発した。これらのツールや公開された資料は、ダウンロードして誰でも無償で利用することができる。もっとも、コストダウンにつながるような効果的な導入・活用となると、ツールを使えば可能になるというわけではないのが実状だ。
日本企業のなかで着実に進む導入 MFCAは現場を大きく変える
JMACでは、MFCAの日本上陸以後、30件以上の事例を手がけてきた。その経験から見えてきたことは、『どのデータを用いてMFCAを計算するか』『どのロスを重点的に改善するか』『業務の個性に合わせた現実的な改善案を出せるか』の3点が、MFCA成功のポイントだということだ。導入にあたり、クロスファンクショナルな体制を準備することも重要となる。これらを踏まえ、よりスムーズかつ効果的に成果を出すにはMFCA導入・活用のノウハウが必要となるだろう。
企業側、特に製造・加工業などでは、MFCAを使ってコストダウンに成功しても、その効果を発表しないものだが、MFCAはその有力な手段として着実に結果を出している手法なのだ。
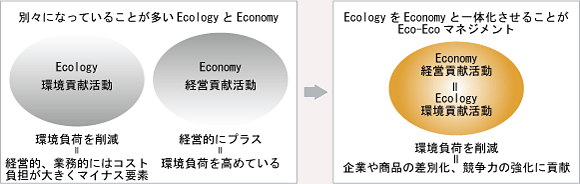
![]()
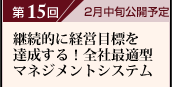
文化と気質の違いを超え、新たなる形に進化した日本の技術と、イタリアのコンサルティング事情もご紹介いたします。