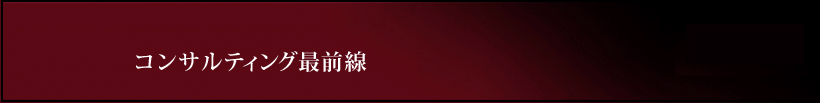数値で結果を判断できるのがMFCAの強み
コスト管理を実施していない企業は、まずないといっていいだろうが、現状の管理システムでは盲点となっているロスが存在するものだ。「通常、歩留管理の対象になっている材料ロスのほかに、副材料・補助材料のロス、切り替え時のロス、それらにかかった加工費・廃棄費用までは、計算していないことが多いのです」と下垣は指摘する。MFCAは、これら“見えないロス”を数字として“見える化”してくれるのだ。
MFCAは、ロスをコストとして定量化する。MFCA導入の際、一般的に、定量的評価として用いられるのは、『廃棄物の発生量』『原材料の使用量』『コストがどう低減したか』の3つの数字だ。どの工程で費用がかさみ、改善の結果、どれだけの利益があったのか、誰が見ても一目で理解できる。
「MFCAによってロスミニマムな生産体制に切り替えた企業のなかには、原材料ロスを8割以上カットできた例もあります。製造・加工業は多岐にわたるので、効果の大小はありますが、現場の改善活動ほか、生産管理・計画、生産技術、研究開発の場で、有効な手段として確実に結果を出せると確信しています」
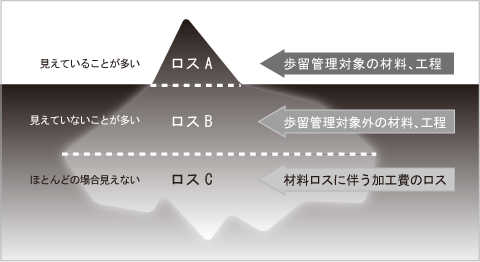
現場への刺激 各分野で全社的視野が身に付く

さらに、MFCA導入は現場への刺激にもなる。担当部門のコストが数字として明示されるため、各部門の担当者は、効率や生産性について意識せざるを得ない。また、導入プロジェクトは部門間を越えたクロスファンクショナルなものとなるので、自然とプロセス全体に対する担当部門の役割のほか、他部門への理解などが深まる。「従来、漠然と集めてきたデータの意味と活用方法を理解した、という声は代表的なものです。また、部門別や工程別に行われがちだったTPM指導やコストダウンも、連携を意識して全社的な視野で取り組めるようになったという例が数多くあります」
その結果、MFCAが評価され、ひとつの工程・部門から複数の工程・部門へと適用が拡大した企業もある。「漸次的に適用を広める場合、既存の生産管理システムとの併用・共存も考えなければなりません。JMACでは、企業の要望に合わせて、導入段階別の活用支援プログラムのほか、導入後のフォローアップも柔軟性をもって対応してきました。MFCA活用の現場では、既存のリソースにうまく組み込むことも必要になります」
![]()
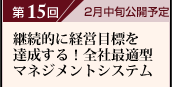
文化と気質の違いを超え、新たなる形に進化した日本の技術と、イタリアのコンサルティング事情もご紹介いたします。