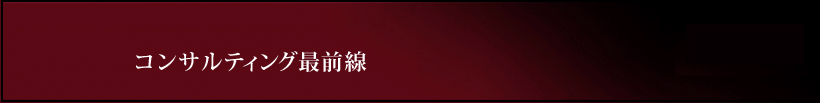働く人をイキイキとさせる 自律型マネジメントの底力

自律型に体質を変えるという点で、石山は印象に残っている企業の例をあげた。「ある通信機器メーカーですが、そこは携帯電話といった進歩が早い分野の製品を手がけているうえに、販売対象が全世界ということで、技術も生産量も変わりやすい状況に翻弄されていました。相談を受けたとき、経営者は全社最適とともに、自律型体質を手に入れることに強いこだわりをもっていたのです。そこで、為替や原材料相場の変動を全社員が見られるようにしました。ラインを担当する人も『為替が変わってきたから、売値が影響を受ける。早めにコストダウンをしないと問題だ』ということに気づけるようにしたのです。しかし、そこでめざしたいのは気づきを自分で行動に移すことですから、指示する形にはしませんでした。その代わり、変動に素早く反応した人の業務を評価する仕組みにしたのです」そこにも、やはり個人差はある。変動幅の1割で対応した人、2割で対応した人、というように、反応の細やかさ別にレベルを決め、各人がどれに該当するかを明確にしたのだ。「できていない人を糾弾するのではなく、できている人を評価したのです。これで、自律的に行動できる人材を増やしていくことができました」
だが、興味深いのはここから先だ。実は、この企業も時代の波を受けて多くの人員が請負会社の社員に入れ替わっている。「めざしていた自律化がどうなったのかヒアリングしてみたところ、今もその仕組みが動いていることがわかりました」この企業では、ライン1本ずつをそれぞれ請負会社が契約している。以前は社員に行っていた評価制度を、請負会社に対して実施しているというのだ。「さらに請負会社は自社社員に対して、同じような評価制度を取り入れています。成果を出したラインには多く発注されるし、そうでないラインには少なめになるという市場経済と同じ競争が起きています」一度、自律型のマネジメントを手に入れた企業は、それを応用して活用する術も身につけていたのだ。「しかも、そこの企業の方をはじめ、請負会社の方たちもすごくイキイキしているのです。これをこう改善したのは自分なのだ、という誇りをもっていました。仕事で自分を、品質を高めていくことそのものが楽しい、という働く喜びがありましたね」その嬉しそうな表情にこそ、日本企業らしさがあると石山は考えている。
新たな価値を提供する 全社最適型マネジメントシステム進化の先
全社最適型マネジメントシステムを展開しながら、石山は次なるニーズの高まりを感じている。「現在適用している範囲では、設計が終わった後、量産体制に入った段階を対象にしていることが多いのですね。しかし、それ以降の段階では、進行している製品の短サイクル化に対応しきれないという問題があります。改革を終えたときには、次の製品が主流になってしまうのです。経営者からは、もっと前の段階、原価企画の時点で全社最適型マネジメントシステムを取り入れていかなければという声を非常に多く聞きます。この要請に応えられる、もっと前段階から対応できる全社最適型マネジメントシステムにしていきたいと思っているところです」目下、石山はこの課題に取組んでいる最中で、比較的早い時期に実現できそうな手応えをもっているそうだ。
「もうひとつ考えていることに、製品競争力があります。たとえば、成熟した市場をもつ製品ではそれ以上の技術改良、コストダウンなどによる価格の切り下げには限界があります」確かに、世間に流通しているさまざまな製品をみても、機能や価格は横並びになりがちだ。優れた機能があるから選ぶというケースは、かつてより減ったといえるだろう。一定の用途、一定のサービスでは、所詮、技術も売上もいつかは頭打ちになり、改善努力にも限界がみえてくる。「現状の技術を新しいビジネスモデル、新しい製品サービスのなかで活用していく形ですね。創造的な発想を生み出し、実際の事業にしていく仕組みを全社最適型マネジメントシステムのなかにもつことはできないかと考えています。今、日本を代表するさまざまなトップ企業と研究会を立ち上げて、共同研究を進めているところです」全社最適型マネジメントシステムが一番高いところに掲げる経営戦略をも、企業と一緒に検討していこうということだ。
海外拠点も含めた最適 そして“世界一”の技術立国復活へ!
全社最適というとき、話は日本国内に留まるとは限らない。海外拠点をもつ企業は少なくないうえ、今後も海外の重要度は増す方向にある。そのとき、日本国内と海外とを合わせて“全社最適”を実現することができるのだろうか? 石山は、そこにも新たな課題を感じている。「日本と海外では運用の仕方を変えているのが実態です。日本では既に述べた4つの“感”で、海外ではそこをインセンティブ制度などで運用しています。その方がうまくいくからですが、本当にそれでいいのか? という疑問はもっています。一例として、海外拠点から日本人の人材を国内に戻したいというニーズが企業側にあるのですね。日本人社員が担っている品質や成果の維持を現地スタッフに移管したい、そのために自律化した仕組みをつくるにはどうしたらいいのか、と新たな課題の登場ともいえます。ならば、異なる運用のままでいいのか、いけないのか…… 議論のあるところです」それでも、全社最適というとき、海外拠点を含めての“全社”である以上、いずれ、何らかの答えを出す必要があるだろうと石山は考えている。
その一方で、石山はもう一度日本を技術立国にしたいという夢ももっている。「日本は以前から技術立国と言われてきましたが、今もそうなのか、と問われると、イエスといえるでしょうか? 巷に溢れる製品ひとつをとってもアジア各国の技術が追いつき、もう日本企業が突出して優れている、だから選ばれるという時代ではなくなっています」しかし、高品質を求めるには、自分たちが扱う技術の本当の限界を知らなければ、“最高”といえるものをつくることは難しい。「たとえば、パソコンや携帯電話など、ある製品の薄さ、それは本当に技術の限界で、この数字になっているのでしょうか?」モチベーションを高めつつ、モノづくりの限界に挑戦できる仕組みをマネジメントシステムのなかに構築したいと、石山は考えている。もともと、日本企業は風土として高い技術力を尊重する傾向がある。世界最薄・世界最速などを実現するために、多大な努力を払うことは珍しくない。「やはり、モノづくりの技術者にとって一番嬉しいのは“世界一”という言葉ですから。全体を最適化、技術力を最高化できるマネジメントシステムが最終的な理想形ですね」石山のいうシステムが具現化したとき、その企業で働く人たちの表情はどこの誰よりも輝いていることだろう。