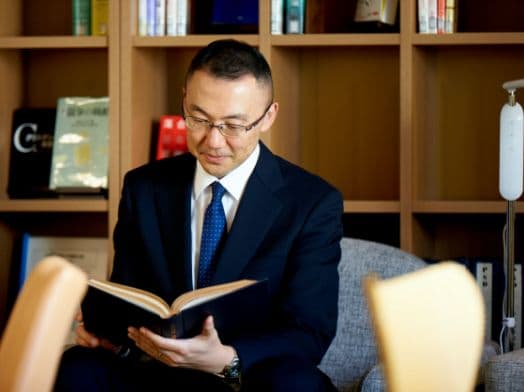エネルギー解析の新たな指標:エクセルギー
第2回 そもそもエネルギーって何?
- SX/サステブル経営推進
![]()
山田 朗

前回の第1話では、熱エネルギーを詳細に計測、解析を行う過程において広く活用されている熱力学第一法則に対して、
- 不可逆な現実に則していない
- エネルギーの質(価値)を考慮していない
という根本的な疑問を述べた。その疑問を払拭する考え方が熱力学第二法則とも関連深い「エクセルギー」であるが、具体的にエクセルギーの話に入る前に、エネルギーや熱の基礎と熱力学法則の不思議な点などについてもう少し深掘りしておこう。
そもそもエネルギーとは
エネルギーという用語はいろいろな場面で使われる。
その種類はたとえば以下のものがある。
- 電気エネルギー
- 熱エネルギー
- 化学エネルギー
- 光エネルギー
- 運動エネルギー
ここで、そもそもエネルギーとは何であろうか?物理学的に言えば、「仕事をする能力」である。仕事は「物体に力を加えて動かすこと」であり、力の単位は[N(ニュートン)]といい、1Nは1㎏の物体に1m/s2の加速度を与える力だ。よってF[N]の力を加えてL[m]だけ動かすときの仕事Wは以下になる。
W=F[N]×L[m]=FL[Nm]=FL[J]
仕事の単位は[Nm]をまとめて[J(ジュール)]であり、エネルギーも仕事をする能力なので仕事と同じ[J]という単位になる。電気はkWh、熱や温度は℃やK(ケルビン)、圧力はPa(パスカル)やbar(バール)、化学エネルギーは重油であればL、ガスであればm3などの単位でそれぞれの量は示されるが、それらの持つエネルギー量や仕事量は全て[J]という同じ単位に変換され同じ物差しで比較検討ができる。
そもそも熱(温度)とは
実際に企業の製造工程で省エネ検討を行う場合には、電気エネルギー、化学エネルギー、熱エネルギーが対象となる場合が多い。とくに熱エネルギーに関しては、ガスや重油(化学エネルギー)を燃焼して蒸気や温水をつくる場合や電気エネルギーを使った電気炉、ヒーター、空調など何らか熱に変換して活用する工程はとても多い。
このように熱の解析は省エネルギーではとても重要であるが、そもそも熱(温度)とは何なのか?実は熱の正体は、熱運動と呼ばれる物質を構成している分子の運動である。分子の運動エネルギーが激しいほど物質温度は高くなる。物質は固体、液体、気体という3態あるが、熱運動が小さいときは分子はきちんと整列し固体の状態を保っている。分子の運動が激しくなると整列が乱れ液体となって分子は流動的に動き出す。さらに運動の激しさが増すと分子は自由に飛び出して気体になる。同じ相、たとえば固体でも温度が高いほど内部の分子の運動エネルギーが大きいというわけだ。分子が全く動かない状態になった時が絶対零度で-273℃(=0K:ゼロケルビン)である。
物体Aから物体Bに熱が伝わるということは、物体Aが物体Bに接触することにより物体Aの分子の活発な運動エネルギーにより物体Bの分子の運動エネルギーが高まる現象である。このように物体が持つ熱エネルギーは、実は物体内部の分子の運動エネルギーなのだ。そう考えると熱エネルギーが他の力学的エネルギーと相互に代替できることがなんとなく分かってくる。
熱力学第一法則の不思議なところ
熱力学第一法則の不思議なところを今一度確認しておきたい。熱エネルギーを解析する場合には、エネルギー保存則を熱に特化した熱力学第一法則を用いて行うことが一般的だ。これは熱と力学的エネルギーの間でのエネルギー量の保存則である。たとえばPLガスをボイラーで燃やして蒸気を作り、反応槽の液体を加熱する場合、LPガスという化学エネルギーが燃焼し、蒸気エネルギーに変換され、更に液体の熱エネルギーに変換されるが、それらのエネルギーの総量は保存される、つまり同じエネルギー量[J(ジュール)]として計算される。
つまり、設備のエネルギー変換効率、設備自体の昇温、放散熱なども考慮すれば、LPガスの持つエネルギー=蒸気エネルギー=液体の熱エネルギーは同じエネルギー量であり、逆の流れも成り立つことになる。この法則の基になっている考え方は、「可逆プロセス」である。可逆プロセスとは、系を初期状態から変化させた後、周囲に何の痕跡も残さず元の状態に完全に戻すことができる工程のことだ。現実の世界ではあり得ない。80℃のお湯は放っておけば15℃の常温になり、何もせずに80℃の状態に戻すことはできない。振り子も時間が経てば止まってしまい、自然に元の大きさで振れることはない。ゆえに永久に動き続ける「永久機関」は存在しないことはみなさんも周知のことだろう。この世の中は不可逆プロセスでできているので、それを踏まえて物理現象を考えることが重要であるのだが、省エネルギーに関連する熱エネルギーを計算する時には、熱力学第一法則だけが独り歩きしている感がある。
さらに言うと、エネルギーの量(エンタルピーという)だけを対象としている。例えば、25℃の水100Lと50℃のお湯50Lの持つエネルギーは、0℃を基準として共に約10MJで同一だ(計算式は質量×温度差×比熱)。しかし、エネルギーの質(価値)はどうだろうか?25℃の水はどこにでもありふれている。50℃のお湯は風呂にも使えるし暖かい飲み物にも役立てられる。50℃のお湯の方がいろいろと使えて便利である。つまり価値が高いことになる。50℃のお湯も放っておけば25℃の価値のない水に変ってゆく。
但し25℃の水は日本では価値が無いかもしれないが、北極に行けば氷を溶かしたり凍えた手を温めたりと価値が高くなる。このように熱の持つ価値は周囲の温度(環境温度という)によっても変化する相対的なものだ。このエネルギーの質(価値)を考慮した、現実の不可逆な世界におけるエネルギー評価の考え方がエクセルギーである。
次回コラムでは、この「エクセルギーとは何か」についてまとめる。
テーマから探す
連載タイトルから探す
JMACライブラリ
-
コラム
JMACコンサルタントがコンサルティングの現場で得た経験や知見、問題解決の視点などをコラムで紹介しています。

-
Business Insights(広報誌)
経営トップのメッセージ、JMACのコンサルティング事例を掲載した広報誌『Business Insights』を公開しています。

-
JMAC TV
JMACが提供する動画配信ストリーミングサービスです。産業界とあらゆる関係組織の経営革新活動の一助として人と組織の成長を支援し、広く社会に貢献することを目的としています。

-
経営のヒント
日本を代表する企業の経営トップの方から、経営革新や価値創造の実例、経営のヒントとなる視点や考え方を伺いました。

-
用語集
JMACコンサルタントがわかりやすく解説するオリジナルの用語集です。基本用語から重要用語までを厳選しています。

-
書籍
JMACコンサルタントが執筆・監修した書籍、技術資料、その他出版物を紹介します。