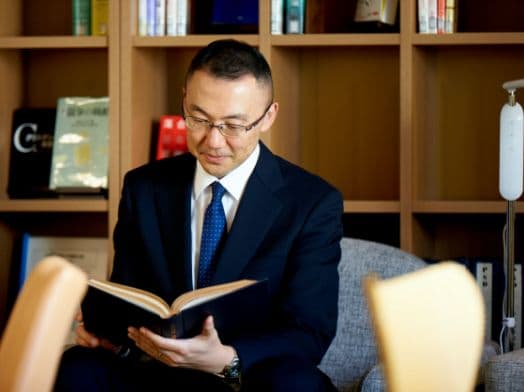「挑戦や遊び」の前提にある思考力は日常から鍛えられる
- R&D・技術戦略
- 人事制度・組織活性化
![]()
大崎 真奈美

去る2024年12月2日に、JMAC主催の第27回R&Dイノベーションフォーラムが実施されました。32名のR&D組織の幹部の方にご参加いただき、盛況のうちに終えることができました。ご来場いただいた皆様ありがとうございました。2025年度は秋に実施予定ですので、JMACからのご案内をお待ちください。
幹部自ら「あそび」を
第27回R&Dイノベーションフォーラムは、「タイパ時代のR&D人材育成」と少々挑戦的なテーマだった。金沢大学の金間先生の基調講演では、最近の若者の特性について共有いただいた。多くの若者がもつ「タイパ思考(自分の時間を無駄にしたくない、与えられた成果以外出したくない、目立ちたくない」価値観は、実は来場者である幹部層を含めた、ほとんど多くの人がもつ価値観でもある。若い人はそれに素直にしたがっているだけで、むしろタイパの価値観と事業環境とのギャップに苦しんでいるのは幹部層かもしれない。金間先生のメッセージはそんな幹部層こそ、なってほしい若者像を率先して実施してほしい、という内容だった。至極全うで難しく、挑戦し甲斐のある課題である。
フォーラムの後半は「あそびを育む」という、タイパの価値観とはまるで逆行するかのようなテーマで提言、議論を行った。
R&D人材育成においては、顧客志向、デザイン思考、アート思考・・・新事業のためのさまざまなスキームの教育がある程度広まっている。ところが、スキームをいくら身に着けても育たない「あそびを育む」という点がR&D組織での課題と位置付けた。「テーマ企画・遂行」に対して「イノベーティブな」とつけると、やったことのないこと、みたことのないもの、知らないことに視野を広げ、コンフォートゾーンを飛び出ていく必要がある。
且つそれらの新規性・専門性が高く上司が直接指導しきれないため、より一層の自主性が求められる。自らコンフォートゾーンを飛びだしていく行動を称して「あそび」と言っている。「あそび」を他の研究員にも期待するのであれば、幹部層も自らの立場で「あそぶ」ことが肝要だ、ということが言えるだろう。フォーラムでご登壇いただいた幹部の中には、自らの「あそび」の実践を紹介してくれた方もいた。
「タイパ」と一見矛盾するようだが、特に研究者テーマ探索においては「タイム」の幅を長期的にとって考えることが重要である。それは単純に期間を延ばす、ということではなく、日々の習慣の積み上げを意味する。「方法論を習得した」からできるようになる世界ではなく、少しずつ挑戦の幅を広げる、とか、毎日顧客のニーズを考える、といったいわば習慣的トレーニングを行っていくことが、長期のタイパである。そのことを管理職も自信をもってメンバーとそれを共有する必要がある。
あそびの前提に必要な、技術者・研究者としての基礎力「わかる」こと
フォーラムでは扱いきれなかったが、実際にはあそびがビジネスにつながるために欠かせないのは「技術者・研究者としての基礎力」である。イノベーション人材育成を語るにあたって、この「基礎力」が語られないことが多いように感じる。
実際に新事業創出や事業拡大の実績がある人たちには共通点がある。筆者がみてきた例をお話しよう。
ある技術職員は若い頃実験をするときに、プロジェクト目標の達成に必要なサンプル数より多めにサンプルをとっていた。そうすることで、単に結果を出すだけでなく、物質の挙動が「感じられる」と本人は話していた(JMACではそれをポテンシャルサーベイと呼んでいる)。
別の役員はまだリーダークラスだったころに、社内の「紙飛行機大会」に出場した。技術者のプライドがくすぐられる組織風土活性化イベントである。彼は、他の出場者に圧倒的な差をつけて優勝した。他の出場者が紙飛行機の設計に知恵を絞る中で、野球部だった彼は紙を丸めて思いっきり投げたのである(次の大会からレギュレーションが変わった)。
また別の役員は、自らイノベーション人材育成の塾を社内で実践されており、想いの重要さを説いている。しかし、実際の指導の内容には「理論で考えるとどうなるのか」「実際に顧客に聞いてみたのか・試してみたのか」「なぜ他社はやらないのか」といった非常にロジカルな投げかけをしている。
これら技術的な成果を上げてきた実践者の礎には、若い頃から蓄積された「現実や真実をわかろうとする」習慣がある。見ようとし、わかるから、変えるべきところ変えてよいところの判断がつく。その上で、挑戦やあそびがあるから、新しい成果につながる。
Only One構想につながる基礎力とは
新事業やイノベーションは結果的な成果として見えるものだが、その過程において重要な研究者・技術者の思考を「Only One構想」と名付けた。
Only One構想する人、しない人
| Only one構想 | 常識的で安全な構想 | |
| テーマの目的 |
高利益率の持続 |
(とりあえず) 出せるアウトプットを出す |
|---|---|---|
| 課題を目の前にしたとき |
なぜ?なに? |
どうやって? |
| トレンドや常識を把握したとき |
常識を疑ってみる |
常識に合わせようとする |
| 大きな障害に巡り合ったとき |
チャンスととらえる |
おわりととらえる |
| なかなかうまく進まないとき |
自分で悩み、有識者を頼る |
自分で悩む、諦める |
| テーマの価値基準をはかるとき |
顧客がどうか |
上司がどうか |
| 反対意見にあったとき |
立場を理解しあおうとする |
相手を非難し、正当化しようとする |
新事業企画やMOTなどを通して、「顧客価値」や「事業性」など、技術・研究テーマにおいて押さえておくべき要点については、広く技術者・研究者に広まってきたように思う。単純に要素技術としての競争力が優れているだけでは売れず「顧客価値は何か」「競争力があるのか」「事業として実現できるための課題があきらかになっているのか」といった点が問われる。
ある程度学びチャレンジすれば、企画書を書くことはできるようになる。しかし、問題はその中身で「面白いか」が重要となる。もう少しビジネス的に言えば、「現存の商品に対して圧倒的な成果を出せる(でも誰もできると思っていない)」「後追い市場に対して圧倒的に逆転できる(でも誰もできると思っていない)」「新しい市場を生み出す(でもそんな市場は今はないので信じられない)」ことによって、高利益率を維持するものであるかどうか。そこを握っているのは、プロセスや型ではなく、技術者・研究者の能力そのものだ。その能力を高めていく習慣の一部が、OnlyOne構想である。
技術者・研究者としての基礎力は、どんなテーマでも磨ける
このOnlyOne構想は、実は技術者・研究者であれば、いつでも鍛えることができる。
話が少し変わるが、「両利きの経営」という概念がある。両利きとは「新事業の創出」と「既存事業の発展」のことを示す。この考え方は自体はよいのだが、「新事業」と「既存事業」を過度に切り離すことは問題ではないかと思う。
既存事業があるということは、顧客との関係性があるということだ。また、顧客との関係性があるということは、新規参入を図る他社に比べて、潜在ニーズを得るチャンスが多いということである。何も顧客との関係がないところからゼロベースで新規事業を立ち上げるよりも、はるかにアドバンテージがある。
ところが、既存事業のスキームが合わないという理由だけですべてを切り離しすぎることで、迷走している「新規事業担当」チームが多いように感じる。既存顧客との関係が重要な資産であることに気が付いていない人が多いかもしれない。
先に上げた新事業創出につながる「技術者・研究者としての基礎力」は、実は既存事業であっても十分活用でき、鍛え上げられるものである。普段から鍛えておけば能力は高まるし、既存事業の中でも顧客に感動を提供できる商品開発ができるのではないだろうか。
イノベイティブな開発とオペレイティブな開発を分けてマネジメントすることは必要だと思うが、「既存事業の開発=オペレイティブである」と思いこみすぎるのも問題である。数多くある既存事業の開発でこそ、イノベイティブな思考を発揮することが大切であると考える。
テーマから探す
連載タイトルから探す
JMACライブラリ
-
コラム
JMACコンサルタントがコンサルティングの現場で得た経験や知見、問題解決の視点などをコラムで紹介しています。

-
Business Insights(広報誌)
経営トップのメッセージ、JMACのコンサルティング事例を掲載した広報誌『Business Insights』を公開しています。

-
JMAC TV
JMACが提供する動画配信ストリーミングサービスです。産業界とあらゆる関係組織の経営革新活動の一助として人と組織の成長を支援し、広く社会に貢献することを目的としています。

-
経営のヒント
日本を代表する企業の経営トップの方から、経営革新や価値創造の実例、経営のヒントとなる視点や考え方を伺いました。

-
用語集
JMACコンサルタントがわかりやすく解説するオリジナルの用語集です。基本用語から重要用語までを厳選しています。

-
書籍
JMACコンサルタントが執筆・監修した書籍、技術資料、その他出版物を紹介します。